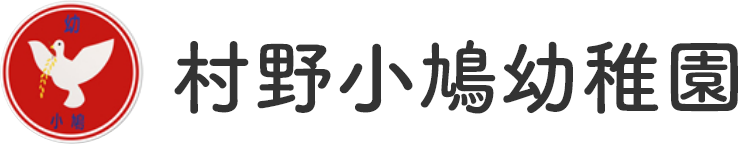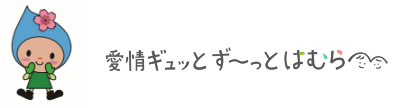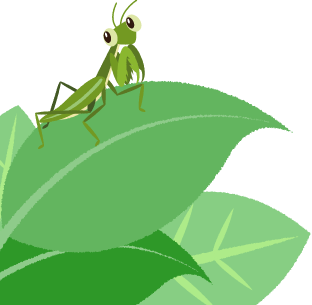保育の特徴
- 遊び
-
幼児期の学習は遊びの中にあるため、当園では遊びを大切にしています。
1人遊び・ルールのある遊び・ごっこ遊び・砂遊び・はだし遊び・みず遊び・泥遊びなど無限にある遊びの中で多くのことを学んでいきます。
その中でも手・足の裏で感じる感覚遊びは子どもの脳の発達を促すため、暖かい日は、はだし遊び・泥遊びを取り入れています。
👩保護者「思いっきり砂場で遊べるのはいいですね~」
🌞先生「そうですね。汚れてしまうことを気にせず思いっきり遊んでいます。」
👩保護者「公園だと汚れてしまうことを気にして「汚さないで~」と言ってしまったり、汚れないよう助けてしまってました。」
🌞先生「幼稚園では汚してしまっても大丈夫!!「沢山遊んだね~楽しかったね~」と声をかけています。汚れてしまた遊び着は保育後に先生達も一生懸命洗ってくれています。「汚さないで~」と叱ったり、汚れないように手助けをすることが間違えではありません。時には叱ることも、手助けすることも大切ですが、週に5日過ごす幼稚園生活の中では、思いっきり遊び、その遊びの中で子どもたちが沢山のことを発見し、気が付けるよう手出し口出しはせずに、だけれど目を離さず見守ってあげることが保育者の役割で子どもたちの成長にとって大切なことだと考えています。日々の生活の中で保護者の方や先生が汚れた洋服、遊び着を洗ってくれていることにも気が付けば、自然と感謝の気持ちが生まれ汚さないように気にかけてくれるようになります。心の成長も大切にしていきたいと考えています。」
👩保護者「あまり口うるさくならないようにきをつけないといけませんねー」
🌞先生「手出し、口出しはせずに、目は離さないことは、簡単なようで難しいことかもしれませんね。」
- 体力づくり
-
ラックスポーツクラブにて体育指導を専門に学んだ講師によって、マット運動・跳び箱・鉄棒・平均台・ボール運動・縄跳びなど楽しく動くことを主眼に指導をおこなっています。
夏期はプール指導もおこなっています。幼児期にできるようになってほしい運動を学年ごとに行っています。満3歳児・年少さんは、音楽に合わせて楽しく体を動かしたり、並ぶ・順番を守る・立つ・座る・しゃがむ・ぬかす・ぬかさないなどのルールを学びながら鉄棒(ぶら下がる) マット(転がる) 飛び箱(登る 飛び降りる またぐ) ボール(転がす 追いかける 投げる 蹴る)などの運動をしています。
年中さんは、音楽に合わせて体を動かしたり、かけっこ、ケンケン、スキップ、両足飛び、手足走り 手足うさぎ跳び 鉄棒(前回り あし抜き回り フジ下がり) マット(前転 後転 ブリッジ 壁逆立ち) 跳び箱(登る 飛び降りる またぐ 飛ぶ) 二人組の運動(抱っこ 手押しぐるま) ボール(両手、右手、左手ボールつき 投げ上げとり 弾ませとり)など行っています。
年長さんは音楽に合わせて体を動かしながらお友達と競争したり、自分自身のスピードを求めるようになってきます。早く走る、速くスキップをする、友達を抜かす、抜かされるなど活動の中で活動を妨げない範囲で競争を楽しむようになります。鉄棒(逆上がり 空中逆上がり) マット(ブリッジ 頭つき逆立ち 側転) 跳び箱(飛ぶ 台上前転) ボール(右手、左手ボールつき コンパスボールつき キャッチボール ドリブル)などの運動をしています。
- 歌や踊り
-
毎日朝の会で歌を歌います。朝の歌、季節の歌(全学年)、クラスの歌(学年に応じた歌)、1年間でたーーーくさん歌います。子どもたちと歌に振り付けをし歌ったり自由に表現をしながら歌っています。
行事の様々な発表に向け歌や踊りを練習する時間も設けています。12月(2024年度は2月)にはお遊戯会もあります。
歌や踊りなど不定期ですが、保護者の方に向けて動画配信もしています。
- マーチング
-
音楽で表現する楽しさを培っていくうえでマーチング活動を取り入れています。
いろいろな楽器・音にふれ、友達と力を合わせ音楽を作っていく楽しさ、難しさを感じながら、「協調性」「忍耐力」「努力」を培い達成感を味わう事が出来るような指導をしています。
また、敬老会・地域のイベントやお祭り・運動会・お遊戯会で発表する機会をもうけており、
たくさん発表する経験を重ねる事により、大人になっても人前で堂々と話ができる力(度胸)につながっていきます。
課外活動として毎週水曜日の保育後14時から15時30分までマーチングクラブ活動をおこなっております。 - 創作意欲
-
心の表現である絵を描く事や空き箱で創意工夫をして自分の思いを表現する事も子どもたちにとっては大切なことです。
全学年毎月1~3枚の絵を描いています。年中さんからは個人持ちの絵の具セットを使い絵を描いています。混色や配色を楽しむ姿があります。小学校では絵の具セットの管理は自分でしますので、年中さん・年長さんの2年間で絵の具の使い方や、後始末の仕方を学んでいきます。
- 異文化に触れる
-
2週に1回英語教師をまねき、「英語で遊ぼう」をテーマに英語教育を導入しています。全学年それぞれ30分の時間を設けています。毎年カリキュラムを見直し、行事や発達にそった内容にしています。歌、ゲーム、カードなど子どもたちが楽しく取り組める内容にしています。講師の先生は活動中はなるべく日本語ではなく英語で話しています。
- 「なぜ?」「どうして?」を大切にした保育
-
大人にとっては当たり前の事や疑問に思わない事でも、子どもにとっては「なぜ?」「どうして?」と思う事ばかりです。
科学タイムの時間(年中から卒園までの2年間で12回)を通して、専門講師2名が子ども達の身近にある疑問に思うことを教材を使って自ら気づき、発見できるような指導をおこなっています。毎回子どもたちが学んだ事のレポートと、テーマに沿ったキッドをお土産でいただき、ご家庭に持ち帰ります。おうちでも「見てみてーー今日これやったよー」と披露してくれる姿が見られると思います。保護の方もどんなことをしているのかを知ることが出来て安心ですし、子どもたちはおうちでも楽しく考えることが出来ます。 - 自ら考える事を大切にした保育
-
どんな小さなことでも自分で考える事はとても大切です。
普段の保育の中や様々な活動の中で子どもたちが考える事が出来る声掛けをしています。子どもたちの成長にっとって1番大切なのが声がけであると考えています。大人に「●●したら?」「●●でしょ」教えてもらうことも大切ですが、幼稚園では「どうしたらいいかな?」「どうする?」「教えて~」と保育者が答えを言うのではなく、些細なことも子どもたちに問いかけ考えることが出来るよに声をかけています。
また子どもが困っていたり、戸惑ったときも「どうしたの?」と聞くようにしています。子どもたちを見ていたら困っている理由も、どんなことで戸惑っているかも、大人はわかりますが、子どもたちの言葉泥棒にならないようにしています。
- 行事を大切にした保育
-
生活の節目にある年中行事や、保育活動の節目にある保育行事、保護者の参加する行事を大切にし、子ども自身が楽しく関われるような配慮をしています。また子どもたちは一つの行事を終えるとやり遂げたという満足感を味わい、自信と強さをのぞかせます。
保護者の方も忙しい日々の中で少しだけ手を休め、わが子を見つめ成長を感じることが出来ることと思います。
大人(親)の本気を子どもたちに伝える行事があってもいい!!
🌞先生 「世の中はコロナ禍を経験し、幼稚園、学校をはじめ行事の見直を余儀なくされました。人のかかわりは制限さ れ触れることさえ許されない時期もありました。運動会も体育発表に内容をかえる幼稚園も多かったと思います。
小鳩幼稚園の運動会は、年長児が主となり、全園児で協力し、助け合って進めていきます。
それだけではなく40年以上前から「運動会の最後に保護者の本気を見せる日」なんです。」
👩保護者 「それは・・・・??」
🌞先生 「運動会の最後は園児から保護者へと続く全員リレーがあります。」
👩保護者「それは大変。」
🌞先生 「走るのが苦手な方も、得意な方もいらっしゃると思います。そこは、助け合いです。走るのが遅くても大丈夫です。大人も助け合い、本気で挑戦する姿は子どもたちの心に響きます。転んでしまう保護者の方もいますが、立ち上がって走る姿は子どもたちに、どんな時もあきらめない事、立ち上がるたくましさをどんな言葉より強く教えてくれます。(ただしばらくの間は「パパ・・リレーでころんだよね(-_-)・・・・・」と言われてしまうかも。)
子どもの成長を見るだけが行事ではないと思うので、1年に1回。大人も本気を見せてくれるのが小鳩幼稚園の運動会です。」
👩保護者 「大変だけど、楽しそう!!」
🌞先生 「大人も楽しむことって大切ですよね。1年に1回本気を出すのって楽しいいですよ~。大人パワーを大爆発で参加してください。怪我をしていたり、持病があったり、参加できない方は参加NGです。応援も大切なので、全力応援をお願いします。あと、参加して怪我をするのもNGです。」